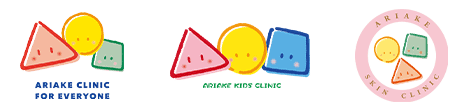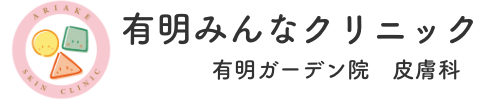2024.12.23 「相手を理解しようとしてから理解されよう」
「7つの習慣」第5の習慣である「相手を理解しようとしてから理解されよう」は、医療現場において特に重要な考え方です。医療スタッフが患者様の言葉だけでなく、その背景や感情に耳を傾けることで、信頼関係が深まり、より良いコミュニケーションが可能になります。本記事では、この習慣を実践するための具体例やアプローチについて解説します。

記事内容
患者様との信頼構築に必要な「7つの習慣」第5の習慣
「7つの習慣」で語られる「相手を理解しようとしてから理解されよう」は、日々の診療や患者様対応において非常に実践的なアプローチです。この習慣を実践することで、患者様に安心感を与え、より深い信頼関係を築くことができます。
例えば、予約が取れず困っている患者様に空き状況を説明するだけではなく、「それは大変でしたね」と相手の気持ちに共感する一言を添えることで、患者様の心に寄り添う対応が可能になります。この小さな配慮が、患者様の満足度を大きく向上させます。
実践例: 感情に耳を傾けることの重要性
患者様との会話では、言葉そのものだけでなく、その背後にある感情や意図を理解することが求められます。スティーブン・R・コヴィー氏が述べたように、耳で聞くだけでなく、心で聞くことが重要です。具体的には、以下のような対応が挙げられます:
1. 共感の姿勢を示す
例えば、患者様が診療の待ち時間に不満を抱いている場合、すぐに言い訳や説明をするのではなく、「長い間お待たせしてしまい、申し訳ございません」と共感を示すことが信頼を築く第一歩です。
2. 背景を理解する質問を投げかける
患者様が感じている困難の背景を知るために、「どのようなことでお困りでしょうか?」と質問を投げかけることで、患者様の本当のニーズを把握できます。
3. 行動で信頼を示す
共感の言葉に加え、迅速な対応や代替案の提示などの行動を通じて、患者様に「理解されている」と感じていただくことが大切です。
第5の習慣の医療現場での活用方法
日常業務の中で、第5の習慣を活用するためのポイントは以下の通りです:
• 患者様の表情や声のトーンにも注意を払う
言葉だけでなく、非言語的なサインにも敏感になることで、患者様の本当の気持ちに気づけます。
• スタッフ間でも実践
同僚や部下とのコミュニケーションでも、この習慣を実践することで、チーム全体の連携や雰囲気が向上します。
まとめ
医療現場では、正確な診療とともに、患者様の気持ちに寄り添う姿勢が信頼関係を深める重要な要素となります。「7つの習慣」の第5の習慣である「相手を理解しようとしてから理解されよう」を日々の業務に取り入れることで、患者様にとって信頼できる医療環境を提供できるはずです。
これからも患者様との信頼を築くため、私たちは努力を続けてまいります。
ブログへの投稿ポイント
• 本記事の冒頭に「信頼関係を築くヒント!」などのキャッチフレーズを加えると読者の関心を引きやすくなります。
• 実践例をさらに具体化(患者様の実際の声など)すると、より読者に響く内容になるでしょう。
• 最後に「7つの習慣」シリーズの次回内容について予告を加えることで、シリーズ化したブログ投稿が可能です。