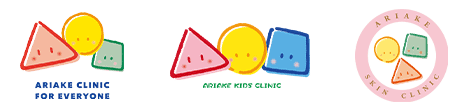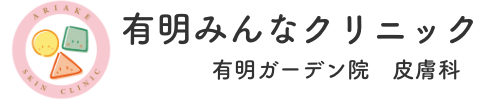2024.12.30 「患者様が感じる安心感」
今回は「7つの習慣」の第5の習慣である「相手を理解してから理解される」を職場にどう応用するかについて発表された内容を基に、患者様や同僚との信頼関係を築くためのコミュニケーションのポイントをお伝えします。正しい言葉遣いだけではなく、相手の心に響く伝え方を意識することの大切さを具体例を交えながら解説します。

信頼関係を築くためのコミュニケーション
「相手を理解してから理解される」という習慣は、まず相手の気持ちや状況をしっかりと受け止めることから始まります。医療の現場では患者様が不安を抱えることが多いため、その不安に共感する姿勢を見せることが信頼構築の第一歩となります。
例えば、診療後の患者様に「これは標準的な処置ですから問題ありません」と説明するだけでは、不安を完全に取り除くことはできません。その代わりに、「お不安な気持ちはよく分かります。一緒に状況を見ながら進めていきましょう」といった言葉を添えることで、患者様が感じる安心感は大きく変わります。
言葉の選び方と心の響き
正しい情報を伝えることはもちろん重要ですが、それ以上に「どう伝えるか」によって相手の受け止め方が変わります。ただの事実伝達に終わらず、相手の立場や感情を考慮した伝え方を心掛けることで、信頼が深まり、より良いコミュニケーションが生まれます。
職場でも実践できるポイント
1. 相手の話をじっくり聞く: 相手が本当に伝えたいことを理解するために、言葉だけでなく表情や仕草にも注意を払いましょう。
2. 共感を示す: 「それは大変でしたね」「お気持ちわかります」といった共感の一言を添えるだけで、相手は安心します。
3. 適切な言葉を選ぶ: 正しい情報だけではなく、相手の心に寄り添う言葉を選びましょう。
信頼関係が職場にもたらす効果
このようなコミュニケーションを継続すると、患者様だけでなく同僚との信頼関係も深まります。結果として、職場全体の雰囲気が良くなり、効率的で生産性の高いチーム作りが可能になります。
まとめ
「7つの習慣」の第5の習慣である「相手を理解してから理解される」は、私たちの日々のコミュニケーションに欠かせない重要な教えです。患者様や同僚との対話で、相手の気持ちをしっかりと理解し、それに基づいた言葉を選ぶことで、より深い信頼関係を築くことができます。この習慣を意識して、共感と信頼を大切にしたコミュニケーションを実践していきましょう。
このような習慣を活かすことで、職場環境の改善や患者様との関係強化が期待できます。ぜひ日々の業務に取り入れてみてください。