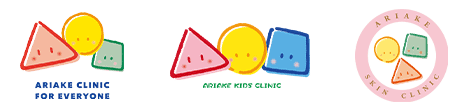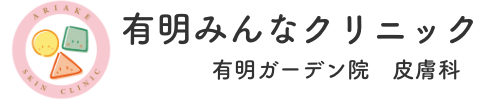2025.09.10 「共感的傾聴」
私たちが日々の仕事や人間関係の中でより良い関わりを築くために役立つ考え方として、「7つの習慣」があります。その中の第5の習慣は「まず理解に徹し、そして理解される」というものです。これは、相手の心を開くためには、まず自分が相手を深く理解しようと努めることが大切だという教えです。
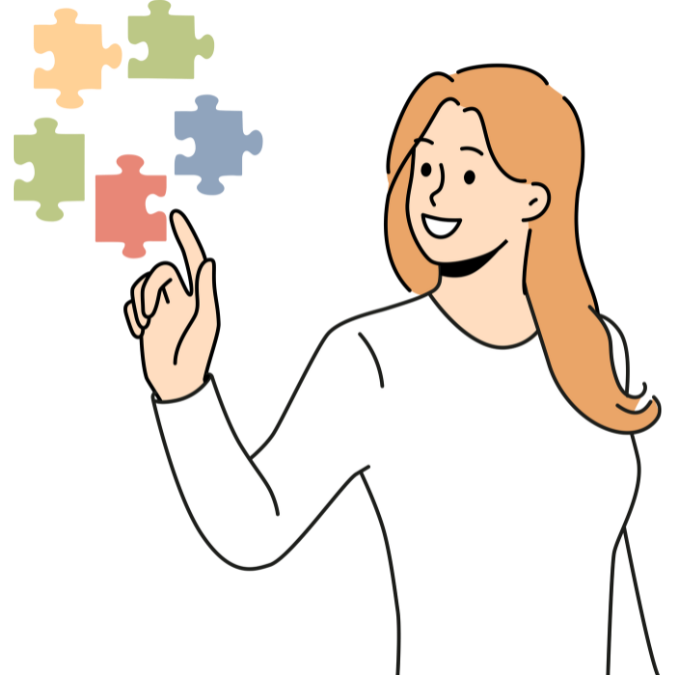
この習慣には聞き方の段階があり、その中で最も深いレベルにあたるのが「相手を理解する聞き方」、いわゆる共感的傾聴です。単に言葉を聞き取るのではなく、その言葉の奥にある気持ちや不安、背景を受け止めようとする姿勢が求められます。たとえば、患者様が「この薬は効くんでしょうか」と口にされたとき、表面的には薬への疑問ですが、その奥には「長く症状が続くことへの不安」や「副作用への心配」といった感情が潜んでいることがあります。その思いに気づき、理解しようとすることで、患者様は安心し、こちらへの信頼を深めてくださいます。
医療事務の仕事は、受付や会計などの事務作業にとどまらず、患者様が安心して診察を受けられるように環境を整える役割があります。そのためにこそ、この「相手を理解する聞き方」が大きな力を発揮します。相手を理解しようと努める姿勢は、医療の場に限らず、日常生活や人間関係全般でも重要です。まず理解に徹することが、信頼と安心を生み出し、より良い関係を築いていく基盤になるのです。