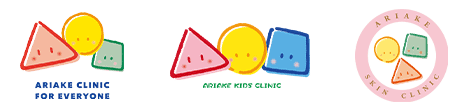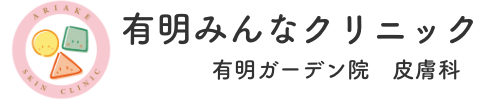2025.03.12 「個々のスキルを活かしながらチームとして協力し合う」
日々の業務を円滑に進めるためには、個々のスキルを活かしながらチームとして協力し合うことが重要です。そのために役立つのが「7つの習慣」の第6の習慣である「シナジーを作り出す」という考え方です。これは単なる協力ではなく、それぞれの違いを活かし、新しい価値を生み出すことを意味します。
職場にはさまざまな価値観や考え方を持つ人が集まっています。意見が異なることは決して悪いことではなく、むしろ強みとして活かすことができます。シナジーを生み出すためには、まず「相違を尊重する」ことが大切です。自分とは異なる視点を受け入れ、そこから新たな可能性を探ることで、これまでにないアイデアが生まれることがあります。

また、単なる妥協ではなく、互いのアイデアを掛け合わせてより良い解決策を見つける「創造的な協力」も重要です。例えば、業務改善を検討する際に、受付スタッフ、看護師、医師それぞれの視点を取り入れることで、現場に即した最適な解決策を導き出せるかもしれません。このように、一つの視点にとらわれるのではなく、多角的なアプローチを意識することが、より良い職場環境を作る鍵となります。
さらに、「第3の案を見つける」という発想もシナジーを生み出す上で欠かせません。意見が対立したときに、どちらかの案に決めるのではなく、双方の意見を組み合わせた新たな解決策を模索することで、より大きな成果を生むことができます。特に医療の現場では、患者さんの対応において多職種が協力しながら最善のケアを提供することが求められます。
職場でのチームワークを最大化するためには、それぞれの役割を果たしながら、互いの強みを活かして補い合うことが必要です。ただ業務を分担するだけでなく、相手の得意な部分を活かしながら協力することで、より大きな成果につながります。トラブルが発生した際も、一人の視点だけで解決しようとせず、周囲と連携しながら多角的に対応策を考えることが、より良い解決につながるでしょう。
「シナジーを作り出す」という考え方は、職場のチームワークを強化し、より良い成果を生み出すための重要な習慣です。日々の業務の中で、相手の意見を尊重しながら協力し、新しい価値を生み出せるよう意識していきましょう。